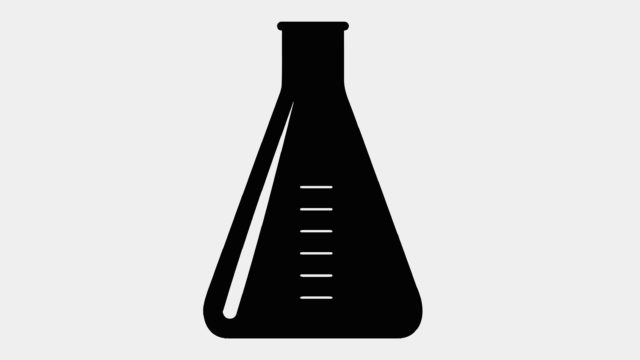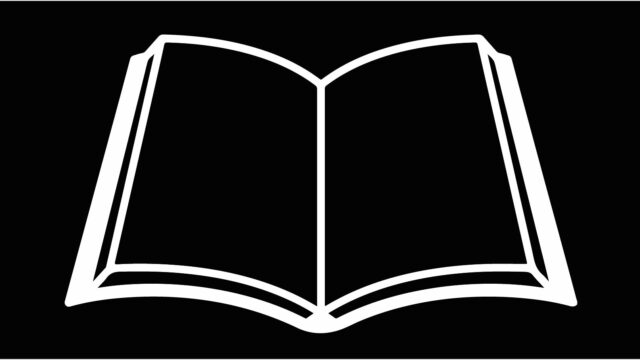さっそくですが、今回は映画のレビューをしてみたいと思います。
映画のタイトルは「小さな命が呼ぶとき」(英語タイトル:Extraordinary Measures)。
こちらは、アカデミアや製薬企業で研究をされているかた全員にオススメできる映画です。
また、コロナワクチンのように、「科学の力が実臨床を大きく変える」そのプロセスが垣間みれる素晴らしい作品だと思います。
あらすじ
この映画は、ジョン・クラウリーという実在する人物をベースとした物語です。
彼には、「ポンペ病」という難病をもつお子さんが2人おり、作品当時は治療法が一切なく、平均寿命が9歳前後と言われていました。
作中、彼はわが子を救うべくして、その研究分野の第一人者ロバート・ストーンヒル博士(ハリソン・フォード)とタッグを組んで、新しい治療薬の開発に取り組んでいきます。
ジョンはもともとハーバード卒のエリートで大手製薬企業に勤めていました。
しかし、そんな彼が地位・名誉・財産のすべて捨てて、果敢にも新薬の開発に挑戦していきます。
重要なポイント
この映画は、実話を元にしているだけに、新薬が登場するまでの過程がリアルに描かれています。
具体的には、
・大学の研究者(アカデミア)と製薬企業の研究スタンスの違い
・莫大な開発費用を調達する難しさ
・企業買収などの政治的なやり取り
・利益相反などの規定
など
良かった点
ここでは、独断と偏見で選んだこの映画内のベストフレーズをご紹介します。
(これは主人公と博士が資金調達に関して、喧嘩したときの会話です)
主人公:Spend the rest of your life dreaming up great ideas and don’t get funded! Draw brilliant diagrams on the wall to cure diseases in theory, but never help a single human being in reality!
意訳:資金を調達せず、素晴らしいアイデアだけを夢みて余生を過ごせ!理論的に病気を治す素晴らしい図面を壁に描いても、現実世界では誰も救われない!
当然ながら、すべての医学研究が実際の診療に還元されるわけではありません。
また、ヒトを救えるかどうかで研究の優劣はつきません。
「研究のための研究」もとても大切です。
しかし、医学研究において、その内容が「どうやったら患者さんへ還元されるか」を常に意識しておくことは大切なのかなと、このフレーズを聞いて思いました。
実際、この言葉を言われた博士もこたえたらしく、
(´·ω·`)ショボーンとします(笑)
最後に
ネタバレは避けますが、この映画は予想通りハッピーエンドで終わります。
私は、父親の子に対する深い愛情、命を救うための行動力にひたすら圧倒されました。
映画の途中、大手製薬企業の同僚がすべてを捨てて退社しようとするジョン・クラウリーを切実に止めようとします。
恐らく、私自身も親友が同じようなことをしたら、きっと全力で止めることでしょう。
しかし、これほどの大業を成すには常人には計り知れない情熱、さらには周りに惑わされない固い意志が必要なのかもしれません。
最後に、ジョン・クラウリー氏が実際はどんな感じの人か興味があったので、映画を観終わったあとにネットで調べてみました。
その時に、全国ポンペ病患者と家族の会のホームページで彼のビデオメッセージをみることができました。
そちらをみると、さらにハッピーな展開が分かります。
以上、最後まで読んで頂きありがとうございます!