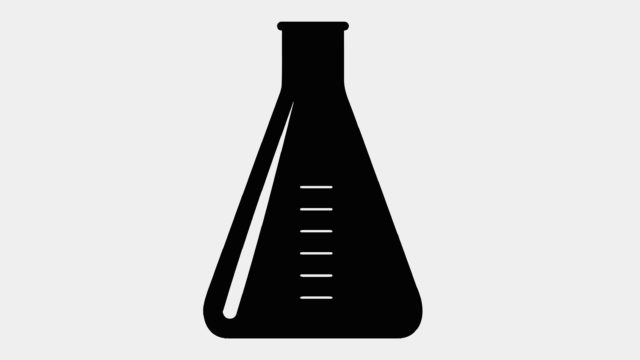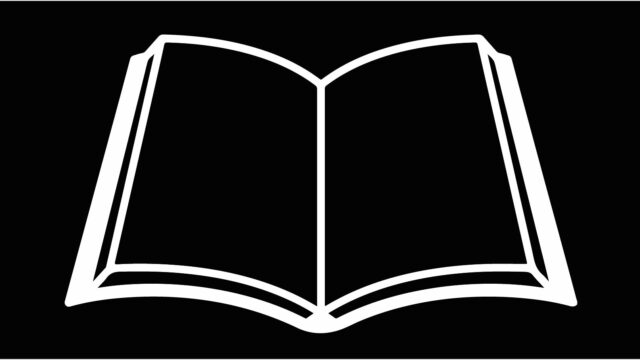先日、1泊2日で臨床研修の指導医講習会というものに参加してきました。
こちらを受講したことで晴れて厚生労働省の定める指導医(=研修医に対する指導を行うために必要な経験及び能力を有している者)と認定され、さらには、臨床研修に関わる多くのことを学ぶことが出来ました。
今回はその中でも特に興味深かったことを記事にしたいと思います。
目次
人を励ます言葉, モチベーションを上げる方法 PEP TALK
今回「モチベーションの上げ方」というセッションで「魂に火をつける講演家」こと浦上大輔先生の講義を聴くことが出来ました。
当日の浦上先生のプレゼンテーションが秀逸だったこともあり、聴講者参加型のとても楽しいセッションでした。
そこでは主に PEP TALKという声掛けの手法について言及されていました。
PEP TALK とは本来はスポーツの試合前に監督が行う激励のショートスピーチを指します。
最近では、大坂なおみ選手を4大大会の優勝に導いたサーシャ・バイン元コーチが使っていたことでも有名になっているそうです。
公演の中では、実際にあった少年野球チームを声掛けによって優勝まで導いた経過が具体例として示されていました。
以下に、PEP TALKについて自分が大事だと思ったポイントを記載しましたが、恐らく初見だと分かりにくいと思います。
そのため、少しでも興味が出た方は浦上大輔先生が直接 PEP TALKの詳細を記した東洋経済のコラムをぜひ読んで頂ければと思います。
勝つために厳しくは必ずしも結果に直結しない ペップトークの活用でチームは劇的に変わる | リーダーシップ・教養・資格・スキル | 東洋経済オンライン (toyokeizai.net)
その他、分かりやすい解説動画「PEP!Tube」がyoutubeで無料閲覧できるのと、本で学ぶことも出来るのでご参考までに。
たった1分で相手をやる気にさせる話術 ペップトーク, 浦上大輔, フォレスト出版
PEP TALK のルール
まず、この声掛けのお作法について記載します。
※左側がPEP TALKの要点で、右側がその対比となります。
ポジティブな用語で ⇔ ネガティブな言葉で
相手の状況を受け止め ⇔ 相手のためと言いながら
短くて分かりやすい ⇔ 延々と
人をその気にさせる ⇔ 人のやる気をなくす
言葉がけ ⇔ 説教、命令
繰り返しになりますが、まとめると
ポジティブな用語で、相手の状況を受け止めつつ、短くて分かりやすい、さらに、人をその気にさせる言葉がけ
が大事になってきます。
PEP TALK の4ステップ (※参考文献:講演のハンドアウト)
次に、PEP TALKでは以下の4ステップを1.から順に行っていくことが重要とされています。
各ステップのコンセプトと具体的なフレーズをまとめてみました。

1. 受容:今置かれている事実を受け入れ、不安や緊張を和らげる。
① 状況受容:
「相手は全国大会の常連校だ」
「今日は第一志望の試験の日」
「これから大事なプレゼンだ」
② 感情受容:
「緊張するのは当然」
「不安になるのも分かるよ」
2. 承認:事実の捉え方をポジティブに変換し、感情をプラスに持っていく。
① とらえかた変換:
緊張 →「本気の証拠だよ」
不安 →「誰よりも勝ちたい思いがある」
ピンチ → 「成長のチャンス」
② あるもの承認:
「今まで誰よりも頑張ってきた」
「誰よりも勝ちたい思いがある」
「一緒に挑戦する仲間がいる」
3. 行動:2.で変換した捉え方を、どう行動に移せばいいか示す
① ネガ → ポジ変換
「ミスするな」→「自分の力を出し切れ」
「焦るな」→「落ち着いて」
「緊張するな」→「笑顔で楽しもう」
② 結果 → 行動変換
「勝とう」→「ベストを尽くそう」
「シュートを決めろ」→「思いっきり打て」
「合格しよう」→「問題に集中しよう」
4. 激励:その人の背中を押して本番に送り出す
① 強く押す 「さあ、行ってこい」「君ならできる」
② 優しく押す 「みんなついているから」「大丈夫だよ」
相手の行動を変えて欲しい時に、つい3.から始めがちだが1.から開始するのがポイントのようです。
そして、相手が落ち込んでいる時は1.と2.を繰り返してから、3.に移行するのが効果的のようです。
その他
いきなり PEP TALKを実践しても効果なし。
人のモチベーションを上げるにはまず自分のモチベーションが高いことが前提条件。
自分のモチベーションの上げ方については東洋経済のコラムの方に記載がありました。
ということで、最後が若干投げやりになってしまいましたが、以上が PEP TALK のエッセンスの一部になります。
興味がある方はぜひコラムや動画、さらには本をご確認頂ければと思います。
Learning Pyramid(学習定着率)
PEP TALK以外に、興味深かったテーマとして「学習効率」がありました。
こちらに関しては Learning Pyramidの図だけ載せておきます。

Learning Pyramid とはアメリカ国立訓練研究所(National Training Laboratories)の研究によって導き出された学習定着率を表す言葉です。
より能動的・主体性が必要な学習ほど定着率が高い(=教育効果が高い)ことが分かります。
人に何かを教えるの大変ですが、そのぶん自分への学習効果も高いようです。
最後に
指導医講習会は討議・講義が合計16時間以上あり、他にも勉強になった知識がたくさんありましたが、全てを記載すると膨大な量になるため、今回は特に興味を引いた2点のみ記事にしました。
朝から晩まで分刻みのスケジュールでなかなかハードでしたが、勉強になっただけでなく、普段お世話になっている他科の先生や自分の同期に久しぶりに会うこともできて、大変満足の行く会でした。
もし医師の方で機会があれば、ぜひ参加してみて下さい。
以上、最後まで読んで頂きありがとうございました。