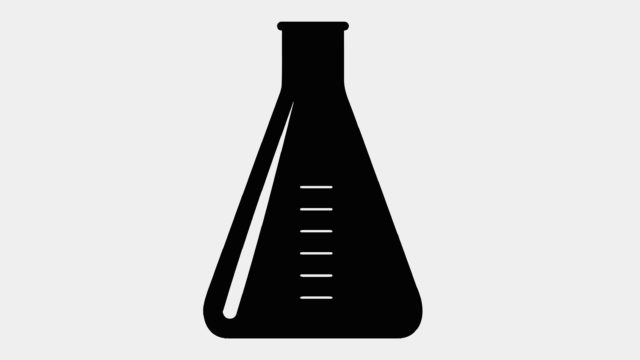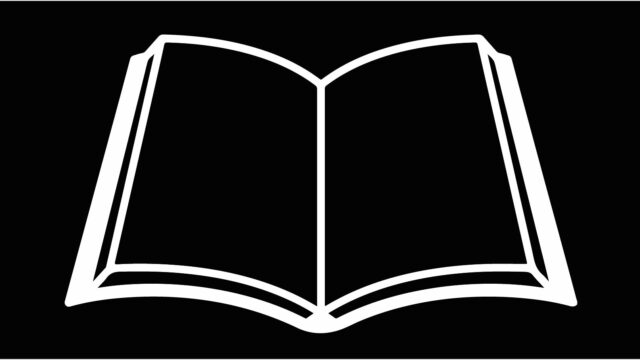読書レビューの第2弾です。
第1弾の「理系のための人生設計ガイド」が予想以上にアクセスがあったので、しばらく読書レビューを続けていこうと思います。
今回、ご紹介する本は「切磋琢磨するアメリカの科学者たち」。
この本は、平たく言うと「アメリカでサイエンスが加速していく仕組み」について、筆者の実体験をもとに書かれています。
研究留学を控えた私にとっては非常に参考になった本でした。
ただ、万人にオススメ出来るわけではなく、以下のような人達にきっと役立つと思います。
・研究留学を志す人(留学が確定してからでいいかも?)
・研究留学中の人
内容
前述のとおり、この本では「アメリカでサイエンスが加速していく仕組み」=「アメリカの科学者たちが切磋琢磨する背景」について書かれています。
その「仕組み」とは、主に以下の3つのシステムで構成されています。
- 大学教育
- ポジションの獲得
- 助成金
著者自身が、アメリカでPhDを取得され、その後、終身雇用を目的とした教員(テニュアトラック)、NIHの助成金申請・審査などを経験されているため、これらのシステムが非常に具体的かつ丁寧に解説されています。
そして、アメリカではこれら3つのシステムが密接に関わりあって、サイエンスが加速しているのだと良く理解できました。
個人的に興味深かったこと
次に、この本で興味深かったことを幾つか紹介していきます。
大学院関連
覚えている範囲で羅列します。
・アメリカの大学院生は給料がもらえる。
・アメリカでPhDを取得する理由:いい就職先を見つける+将来的に高い給料をもらうため。
・日本とアメリカでPhDが社会的に与える印象が違う。
・MD+PhDの与える印象も違うよう。
・優秀な学生を確保するために大学側がやっている工夫。
・研究から得られた知的財産はすべて大学に帰属!そういえば、私も留学準備でそんな文言の契約書にサインしたけど、深く読んでいませんでした笑
・大学が若手研究者にスタートアップ資金を与えるのは、投資の意味合いが強い。つまり、研究者に助成金を獲得してもらい、その間接経費でより多くの資金が大学に入ることを期待している。なので、大学に所属する研究者は、助成金を獲得することが超重要。
研究者関連
自分のボスがどういったプロセスや審査を経て、いまのポジション(Professor)を獲得したのかよく分かりました。
そして、尊敬の念がさらに強まりました笑
その他、覚えている範囲で非常に興味深かったこと。
・役職の違い(日本と全く違う)。ラボメンバーのそれぞれの立場の違いも少し分かりました。
・PIの観点からいうと、Assistant Professor, Associate Professor, Professorの立場は並列。
・休暇中の給料は助成金から捻出する(場合がある)。
助成金システム
日本との違いにびっくりです。
NIHのR01を例にすると、研究計画書だけで実に、25ページ書かなければいけないようです。
個人的に、アメリカのNIH grantで「いいな」と思ったこと。
・年に数回申請するチャンスがある。
・申請書の批評(フィードバック)が具体的で、そこから大いに学べる。
・業績だけでは評価されない。
・非固定メンバーも審査に加わる。
最後に
この本を通して、アメリカの研究者をとりまく環境が日本とは全く違うことが、具体的に分かって良かったです。
これから自分を取り巻く環境がどういったシステムで評価され、どういったプロセスで独立した研究者になっていくのか、そして、その背景を学ぶことが出来ました。
実は、私は本を読み終えたときは、いつも、学んだことをiOSアプリのGoodNotesにまとめています。
しかし、この本はあまりに「学び」が多く、まとめるのが大変だったので、その作業を止めました(笑)
そして、この本を「期間があいたらまた読むべき本リスト」の中に加えておきました(笑)
以上、興味が湧いた方は読んでみて下さい。
では、また乞うご期待!
切磋琢磨するアメリカの科学者たち―米国アカデミアと競争的資金の申請・審査の全貌, 菅裕明, 共立出版.