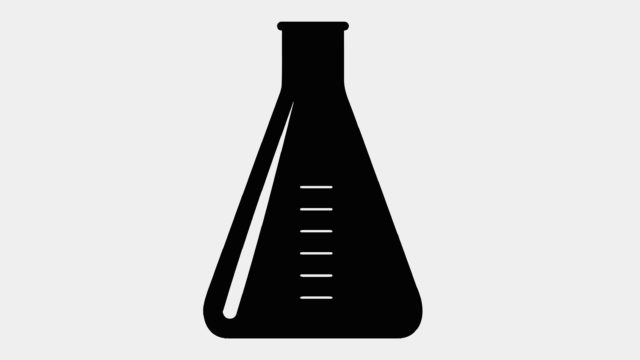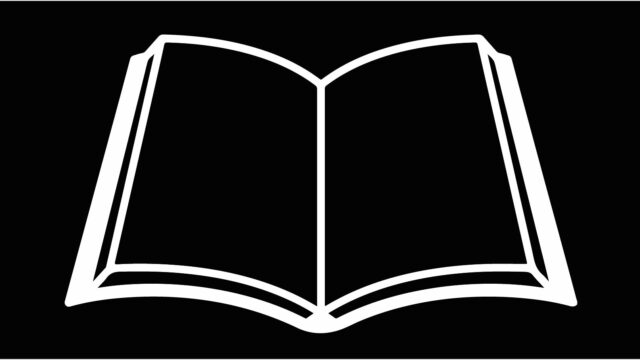ご存じの通り、海外ラボの採用面接では、プレゼンテーションが1つの山場になってきます。
多くの日本人研究者は、豊富な科学知識を持っているものの、それを上手に英語で伝えることが苦手です。
そして、例に漏れず、私もその一人でした…
(私が実際にインタビューを受けた時の様子はコチラです。)
しかし、幸いなことに、これまでに色んなポスドク候補者のインタビューを評価してきたことで、そのノウハウが少しずつ分かってきたように思います。
そして、嬉しいことに、私がフィードバックを提供した3人の日本人研究者が最近、立て続けにそれぞれの第一志望のラボからオファーをもぎ取ることが出来ました。
この経験をもとに、今回は研究者向けプレゼンテーションの秘訣を皆さんと共有したいと思います!

プレゼンの心構えと下準備
- 全員に評価されていることを意識する。
- ゆっくり話すことを心掛ける。
- リハーサルを行う。
- 録画して分析する。
まず、プレゼンのパフォーマンスは研究室の全メンバーによって評価されることを念頭に置きましょう。
そして、プレゼン中は緊張して早口になりがちですが、意識してゆっくり話すことを心掛けて下さい。
また、一人で時間をかけてスライドを作成しても、他者の目からは多くの改善点が見つかることがよくあります。
そのため、本番前には必ずリハーサルを行い、同僚やメンターからのフィードバックを積極的に求めましょう。
さらに、自分の発表を録画することでも、自身の話し方や身振りを客観的に観察できてオススメです。
私は市中病院にいたので、メンターからのフィードバックが受けられず、4年目の先生を捕まえて、リハーサルをさせてもらいました。それでも、とてもいい練習になりました。サンキュー、後輩!
発表のお作法
- 載せたデータは全て言及する。
- 載せたデータは先行論文を含めて全て質問の対象となる。
- 聴衆に直接話しかける。
- 立って発表する。
次に、プレゼンの基本的なルールについて説明します。
まず、スライドに含まれる各データには、一つ一つ言及しましょう。
データを単に掲載するだけでなく、その意味や解釈、重要性を説明することが大切です。
これは言い換えると、あまり言及しない不要なデータはなるべく省きましょう。
これに関連して、例えば、研究背景を説明する際に先行論文のデータを載せたとします。
この場合、それも質疑応答の対象になります。
そのため、最終的なストーリーを伝える上で、不要なデータは可能な限り含めないようにしましょう。
「このプロジェクトでは薬剤Aを使います。」と説明する際に、その構造式を何となくスライドに載せたとしましょう。その構造式が自分のプロジェクトの結論と関わるのであれば、載せた方がいいデータですが、そうでない場合は載せない方がいいと思います。
対面での発表では、スクリーンや原稿ではなく、聴衆に話しかけることを心がけてください。
また、可能であれば、立ってプレゼンテーションを行うことを推奨します。
完全に個人的な見解ではありますが、立つことによって姿勢が改善され、声も大きくはっきりとするため、より効果的なコミュニケーションが実現できると思います。
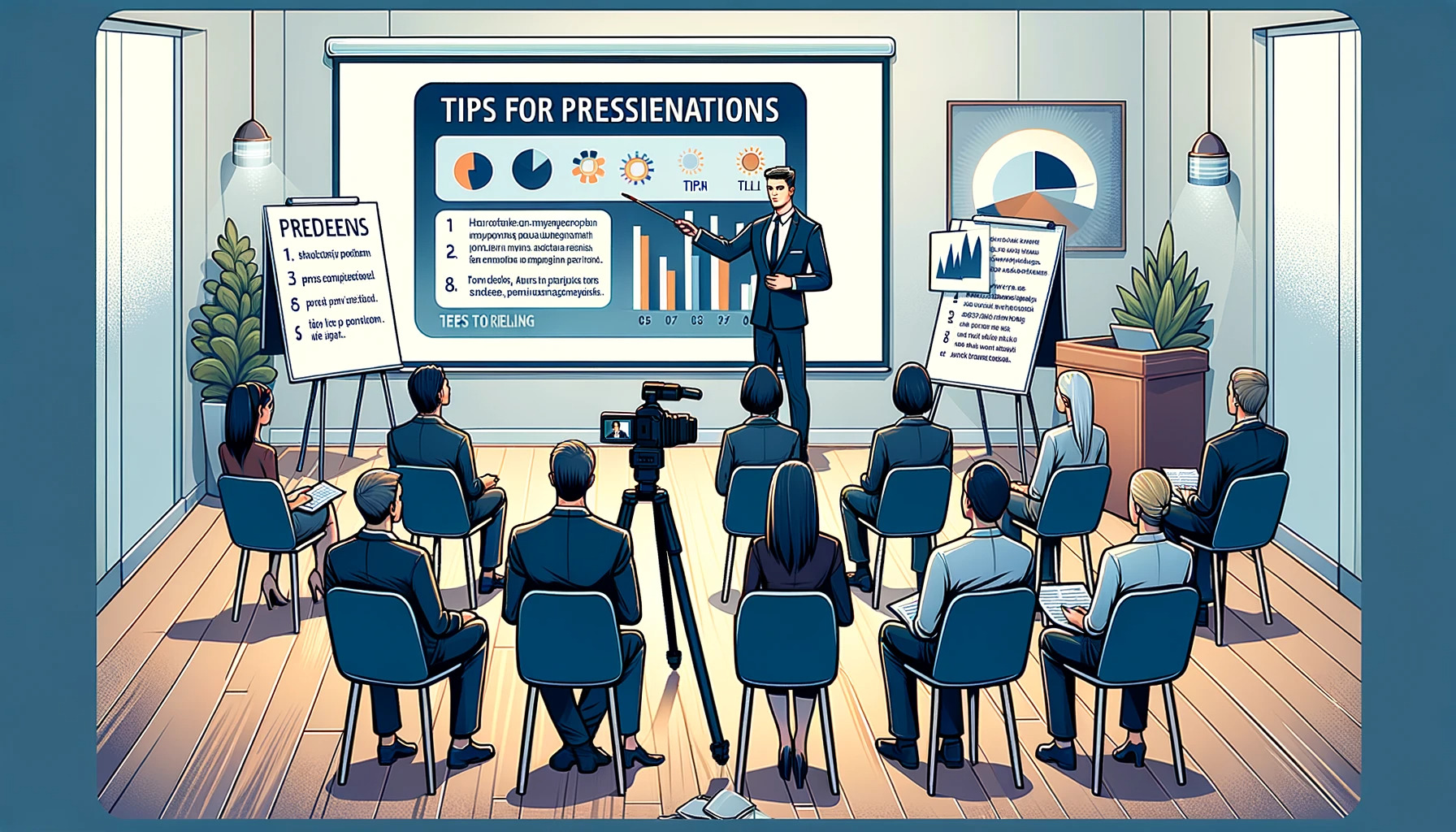
*上の画像はAIが生成しているので、ちょっと英語のスペリングがおかしいですね(笑)あと、よく見るとこっそり足を3本生やした人がいます(笑)
発表の内容
- これまでの研究内容を発表する。
- 臨床研究を含める場合は、適度な範囲にとどめる。
- 研究のプロとして発表する。
ポスドク候補者の面接では、これまでの研究内容が発表の中心になります。
特に医師の場合、臨床研究の業績があるとしても、基礎研究を主体とする留学を目指す場合、それらのスライドは後半に簡潔に紹介する程度に留めておくべきです。
評価者は、あなたの実験データに対する解釈や発展の仕方など、基礎研究者としての資質を重視しています。
もし、臨床研究の実績を基礎研究と結びつけて自身の強みとしてアピールする場合、その研究背景は非医療従事者に向けて、非常に丁寧に説明しましょう。
特に医師の場合、この部分が苦手な方が多いように感じました。
最後に、また、個人的な見解にはなりますが、プレゼンにおいてプライベートな内容の取り扱いには注意が必要です。
例えば、日本人研究者によく見られる自分の年齢の公表や家族写真の掲載は避けた方がいいと思います。
これらの情報は、プレゼンテーションのプロフェッショナルな印象を損なうかもしれません。
あなたの素晴らしい人間性や個性は、ラボメンバーとの個人面談で示しましょう。
スライド作成
- 具体的な研究タイトルをつける。
- 目次を作る。
- ページ番号を載せる。
- 研究背景の説明は、明確かつ丁寧に。そして、簡潔に。
- シンプルで理解しやすいストーリーラインにする。
- 各スライドの伝えたい内容を簡潔なスライドタイトルとして表記する。
- 実験のシェーマを積極的に取り入れる。
- データの一部を掘り下げていく場合、必ずその根拠を示す。
- 長い文章は避ける。
それでは、スライドの具体的な作成方法について見ていきます。
まず、一番最初のスライドでは、あいまいな表現を避け、具体的な研究内容のタイトルを付けましょう。
複数のプロジェクトを発表する場合は、それらを包含する研究タイトルをつけます。
- 「Lab Presentation」
- 「About my PhD project」
- 「Defeating Cancer*」
*情熱的なのは好きですが、これもタイトルとしては抽象的です。
また、自分の名前の横に取得した学位を記載することはアメリカでは一般的で、PhD取得見込みの場合は「PhD Candidate」と表記します。
プレゼンテーション全体の構成としては、最初に目次を示し、次のトピックに移る際も目次スライドを再度表示することで、聴衆が内容を追いやすくなります。
また、各スライドにページ番号を付けておくと、質問者が聞きたいスライドを見つけるのに役立ちます。
研究背景を説明する際は、聴衆の専門分野やバックグラウンドに合わせて明確かつ丁寧に伝えましょう。
背景説明のクオリティは、続く研究データへの興味や解釈に大きな影響を与えるため、この部分には特に注意を払うべきです。
しかし、だからと言って冗長的になってはいけません。
自分のプロジェクトの「Conclusion」につながる背景を簡潔に載せましょう。
やたら注文が多いのは自覚しています(笑)
実際のデータを提示する際は、過剰な情報を省き、シンプルで理解しやすいストーリーラインを心がけてください。
データを多く載せた方が質疑応答が減りそうで、心理的に安心するのは理解できますが、メインの物語を伝えるのに不要なデータは可能な限り削りましょう。
その代わりに、発表に含めなかったデータは質疑応答用に準備しておくことをお勧めします。
そうすることで、質疑応答がスムーズに進行し、あなたの深い知識と丁寧な下準備をアピール出来ます。
次に、データを示すスライドでは、各スライドの伝えたい内容や解釈をタイトルとして、上部に載せておきましょう。
- 実験手技をスライドのタイトルとして載せる。例えば、「Western Blotting」「IHC」など。
また、実験条件が伝わりにくい場合は、実験のシェーマを積極的に取り入れてください。
特に、オミクス解析を行った場合、どのようなサンプルやコンディションで実験を行い、どのような一次/二次解析でデータを得たのかを概要図で示すと聴衆の理解が格段に進みます。
次に、網羅的な解析データを掘り下げていく際の注意点について述べます。
もし複数の候補分子、パスウェイ、または遺伝子変異が同定された場合、特定のものに焦点を絞っていく際は、必ずその理由づけを行いましょう。
例えば、Volcano PlotなどでPositive因子とNegative因子を左右に分けたとします。
ここで仮にPositive因子のトップヒットに着目した場合、なぜNegative因子の方には着目しなかったのか、科学的に説明して下さい。
あとは、パスウェイ解析などで色んな経路がリストアップされつつも、その内の一つに着目した場合、その根拠をしっかりと述べましょう。
必要に応じて、研究背景や先行報告をここで再び挟んでもいいです。
最後に一般的なことですが、スライドに長文を載せるのは避けましょう。
長文は発表者にとっては伝えたい内容を忘れずに済みますが、聴衆が長いテキストを読むことはありません。
プレゼンの後半
- 研究によって何を明らかにしたか最後にまとめる。
- 具体的な夢を語る。
- 実験スキルのリストは不要。
- 謝辞を載せる(協力者や助成金を明記)。
それでは、後半戦です。
ここでは、自分のプロジェクトが具体的に何を明らかにし、どのように科学の発展に貢献したかを簡潔に述べましょう。
そして、プロジェクトを一通り紹介した後は長期的な目標や抽象的過ぎない具体的な夢を語ることで、あなたのモチベーションの高さを示せます。
時折、プレゼンの最後の方で獲得している実験手技をリストアップする方がいますが、この情報はCVに記載するのが一般的です。
なので、プレゼンでは実験スキルは、データとして示しましょう。
珍しい技術を使用したデータがある場合は、それを積極的にデータとして提示することで、ラボに新しいスキルをもたらす魅力的な候補者として映ります。
いよいよ最後のスライドについてですが、ここでは謝辞を入れましょう。
たくさんの研究者と協力してきたことを示し、あなたのチームプレイヤーとしての素質を強調できます。
その他、助成金の獲得経験があれば、ここで取り上げるのもお勧めです。
質疑応答

- 応答の仕方でコミュニケーション能力が試される。
- 一定の英語レベルが必要。
- 質問はクローズドクエスチョンで大量に来ると心得る。
- 分からないことは素直に認める。
さて、ここがプレゼンの最大の難関と言っても過言ではないでしょう。
質疑応答の対応の仕方は、研究者としてのコミュニケーション能力を示す非常に重要な部分なので、気合を入れて望みましょう。
ここでは、自分がどうでもいいと思うマイナーな意見や質問でも「Oh, that’s a very good point. I am guessing that ~~~ とか I will consider including that in my next submission, thanks! 」などと言って、相手の意見を尊重しつつ、自分の考えを伝えましょう。
インタビューの場で、相手の意見に真っ向から反論したり、言い訳っぽい返答をゴニョゴニョ言うのはオススメ出来ません。
常にポジティブコミュニケーションを意識しましょう。
また、プレゼンを発表すること自体は予め練習できるので、英語力はさほど問題にならないと思います。
一方で、質疑応答でディスカッションを行うには、一定のリスニングとスピーキング能力が必要不可欠です。
なので、研究留学を目指すなら英語の勉強は常にしておきましょう。
完全に蛇足になってしまいますが、いまではChatGPTと無限に英会話を練習することが出来ます。
さらには、自分の科学プレゼンを聞いてもらうことも出来ます。
マルチな能力を求められやすい昨今、使えるもんは積極的に有効活用していきましょう!
次に質問を受けるタイミングですが、これは発表の最中に来ることもあれば、最後に一括で来ることもあります。
なので、どちらのシチュエーションにも対応できるように、心の準備をしておきましょう。
質問の多くはクローズドクエスチョン形式であり、これに対しては明確かつ的確な回答を準備しておくことが望ましいです。
また、海外のラボでは質問が大量に来ることも覚悟して下さい。
分からないことがあれば正直にその点を認め、「今後、調べていきたい」といったことを伝えましょう。
最後に
以上が、私が考える研究者向けプレゼンテーションの重要ポイントです。
これらを意識しながら準備を整え、自信を持ってプレゼンテーションに臨むことで、成功の可能性は一気に高まると信じています。
研究者としての自信を持ちつつも、聴衆への敬意を忘れずに、あなたの情熱と研究成果を存分に伝えてください。
当サイトの他の記事では、一般的なプレゼンテーションの技術やPowerPointの効果的な使い方についても触れています。
興味がある方は是非ご確認ください。

それでは、皆さんの成功を心から願っています:)
Good Luck!