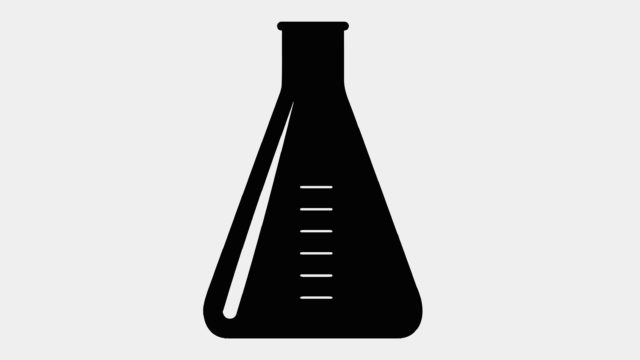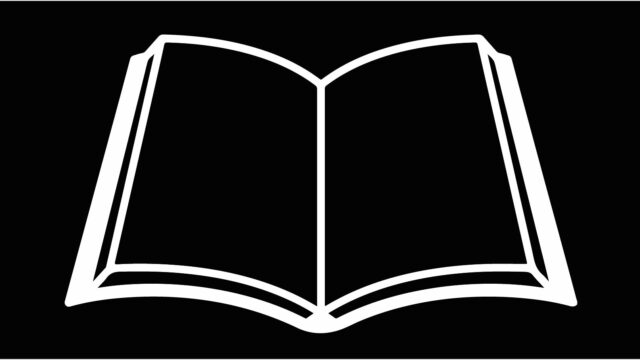渡米してから3か月、勤務を開始してから約2ヶ月が経ちました。
あっという間でしたが、アメリカの生活にも少しずつ慣れてきました。
このタイミングで、渡米後に感じたことを忘れる前に書き記してみたいと思います。
「日本人」の与える印象
まず驚いたこととして、私の所属する大学では「日本人」というだけで好意的にみられることが多いように思いました。
恐らく、アニメやマンガなどを通して日本のことを多少なりとも知っており、日本文化に興味を持っている人が多いのかなと思います。
そして、実際に日本を訪れたことがあるラボメンバーも沢山おり、「くそー!」「ばか」「いただきます」「おかえり」などの片言の日本語をたまに話しかけてくれて、まあまあ面白いです笑
1つ可笑しかった事として、ラボメンバー数人と「ドラゴンボール」の話題になった時に、自分だけが完全に蚊帳の外だったようなエピソードがありました笑
最近では、「鬼滅の刃 Demon Slayers」「呪術廻戦 Jujutsu Kaisen」がこちらでも流行っています。
ラボ内でも「日本人」が好意的にみられますが、それは数年前から在籍していた日本人の方の影響もあると感じています。
その方は皆から好かれており、その様子は先日、盛大に開催された送別会でも伺い知ることが出来ました。
ちなみに、送別会ではみんなで「送る言葉」を色紙に書きましたが、その時のPIの文章が特に印象深かったです。
皆が思い思いに長い文章を書いていた中、一人だけ短文で「You are my family」と。
泣かすぜ、ボス。
話は変わりますが、昨今ではアジアンヘイトなどのニュースもたまに聞こえてきます。
実際に、私の周りでも近くのスーパーでアジア人に対する暴行事件がありました。
しかし、私自身に関していうと、かなり鈍感な方なので恐らく気付いていないだけかもしれませんが、渡米してから人種差別は1回も受けていません。
これに関しては、アメリカの住む地域性なども影響してくるかもしれません。
自分から何かを訴えないと、物事が全く進まないような経験はしましたが、それは「差別」ではなく全員に共通したことであり、そういう文化なのかなと思っています。
ちなみに、訴えさえすれば意外と話が進むところも、アメリカのいい特徴かもしれません。
研究環境

私の所属する大学では、PhDの学生さんは給料を支払われながら、平均5, 6年で1つの論文を書き上げます。
ゆっくり腰を据えて、自分のプロジェクトに集中できる環境は非常に恵まれており、この違いが日本とアメリカの一番の差なのかなと感じました。
また、ラボにもよりますが、いわゆるビッグラボでは莫大な研究費があり、自分の思いついた実験をお金をあまり気にかけずに出来るのも、1つの強みかなと思っています。
ちなみに、これは完全に所属するラボ次第ですが、私のところでは土日は基本的に人がおらず、みな思い思いに日常生活をエンジョイしています。
かといって、平日みっちり実験をしているわけでもなく、割とのんびりな印象を受けました。
もしかしたら、PIの人柄やラボの雰囲気がよく、研究費も潤沢なので居心地がよく、プロジェクトを急いでまとめ上げることに固執していないのかもしれません。
ラボミーティングについて
私の所属するラボでは全体ミーティングが週一回あり、みな積極的に発言していきます。
そして、だんだん白熱してくると、みんな早口になって何を言っているか分からなくなります笑
私自身も存在をアピールするべく、質問やコメントのチャンスをいつも伺っていますが、本来1時間のプレゼンが2時間になったりするレベルなので、なかなか隙が出来ません笑
コロナ禍の制限について
これからアメリカのラボに打診する人が興味を持つかもしれないと思ったので、少し書いておきます。
あくまで私の所属する大学の場合ですが、2021年4月下旬の時点でラボ内の人数制限は解除されました。
そして、しばらくはマスクの着用が義務でしたが、7月からは屋外・屋内ともにマスクは一切しなくてOKになりました。
また、子供の学校に関してですが、こちらは1年ほどリモート授業だったようですが、6月からon-siteに変わったようです。
まとめ

勤務を開始して約2ヶ月が経ちました。
まだ、新しいラボメンバーということで、手加減してもらっている部分もあると思います。
個人的には最高の環境で研究が出来ていると感じており、まずは他のラボメンバーに追い付けるように必死に頑張りたいと思います。
与えられた研究テーマも非常に面白いです。
最後に、毎度になってしまいますが、この環境を与えてくれた沢山の方々のご協力に深く感謝したいと思います。
・家族。
・研究者としてのバックグラウンドを育ててくれた日本の肺がんチーム。
・コロナの最前線で一緒に戦った仲間達。
・呼吸器内科の患者さん。
など