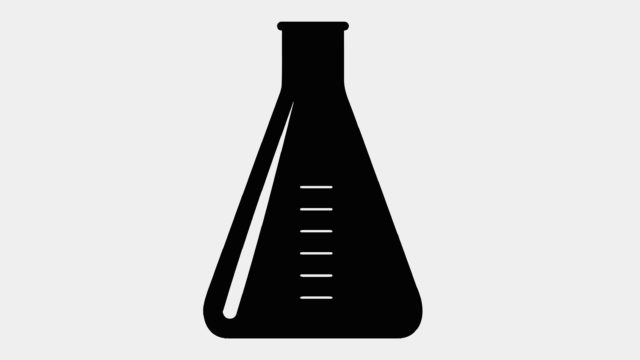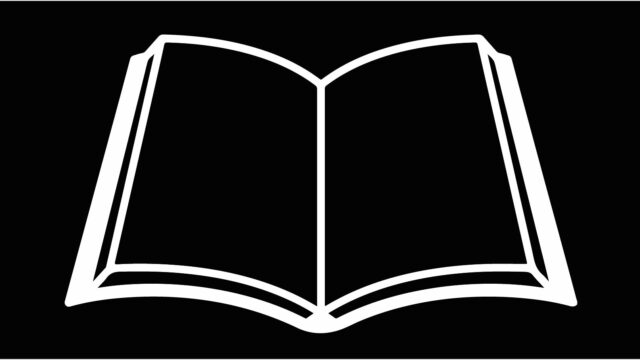ポッドキャスト(英語)で聞く
さっそくですが、今回はポスドクのためのフェローシップ(奨学金)について記事を書いてみました。
言わすもがな、「助成金・奨学金の獲得」はラボの採用条件になることが多く、研究留学の準備における1つの山場ですよね。
なので、研究留学を目指している方であれば、誰でも興味があるところだと思います。
ただ、いざ調べてみると色んな種類があり、私のように何から手を付ければいいか分からない!という方もいることでしょう。
そんな声が聞こえてきそうです。
今回は、そんなあなたのために記事を書いてみましたよ。
ただ正直にいうと、私自身、10か所に応募して最終的に1つしか採択されていません。
ズデーン。
なので、あんまり偉そうなことは言えず、この記事はあくまで参考程度になるかもしれません(笑)
しかし、私のように申請書を作っている時に市中病院に勤務していて、周りになかなか相談できない方もきっといると思います。
主にそんな方を対象に、あくまでn=1ですが、私が「経験したこと」や「振り返ってみて考えたこと」などをこの場を借りて共有したいと思います。
ちなみに、具体的にどんな助成金があるかは、次の記事で言及しています。

2022/08/11追記
留学後、アメリカの有名な助成金にも採択されました。現地のグラントに興味がある方は以下の記事も一読下さい。
アメリカのポスドクフェローシップ成功ガイド:助成金獲得の秘訣と申請戦略
目次
こるく31の成績
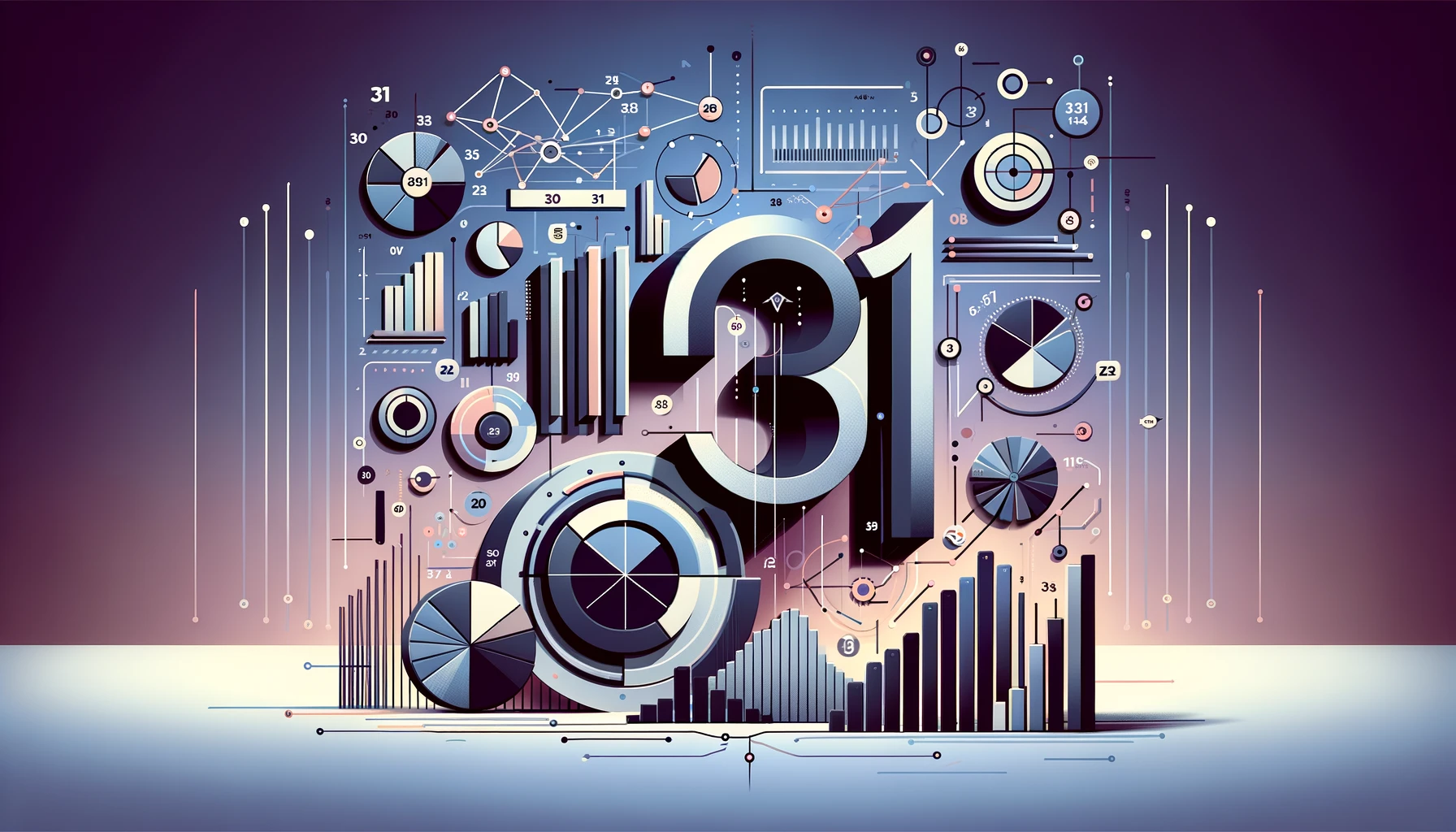
まず、私自身の戦績を詳しくみていきましょう。
これまでの私にとって、助成金の申請といえば「科研費」や「学振」のみだったので、申請書は年1回書くかどうかの平和な世界線を生きていました。
そして、幸いどちらにも採択されています。
また、後輩達の申請書の添削も積極的に行い、多くのケースで採択されてきました。
なので、申請書を書くのは割と自信があったのですが、今回の経験を通して、そのちっぽけな自信とやらは見事に打ち砕かれました(笑)
前述のとおり、私は全部で10箇所の財団の申請書を作成し、1つだけ採択されました(数百万円/年の大型助成金)。
より具体的にみていくと、そのうち学内選考が必要だった助成金は7/10で、その中の4/7で学内推薦を頂くことが出来ました(学内選考については後述します)。
少しややこしいですが、つまり、申請書を10種類かきましたが、うち3つは正式に応募することなく、学内選考の段階で落とされました。
私の所属する大学では学位論文が CNS などの猛者がちらほらいるので、学内選考の結果については、実力以上のものが得られたかもしれません。
それでは、次のセクションから実際の助成金の申請方法について詳しく見ていきましょう。
助成金・奨学金の探し方
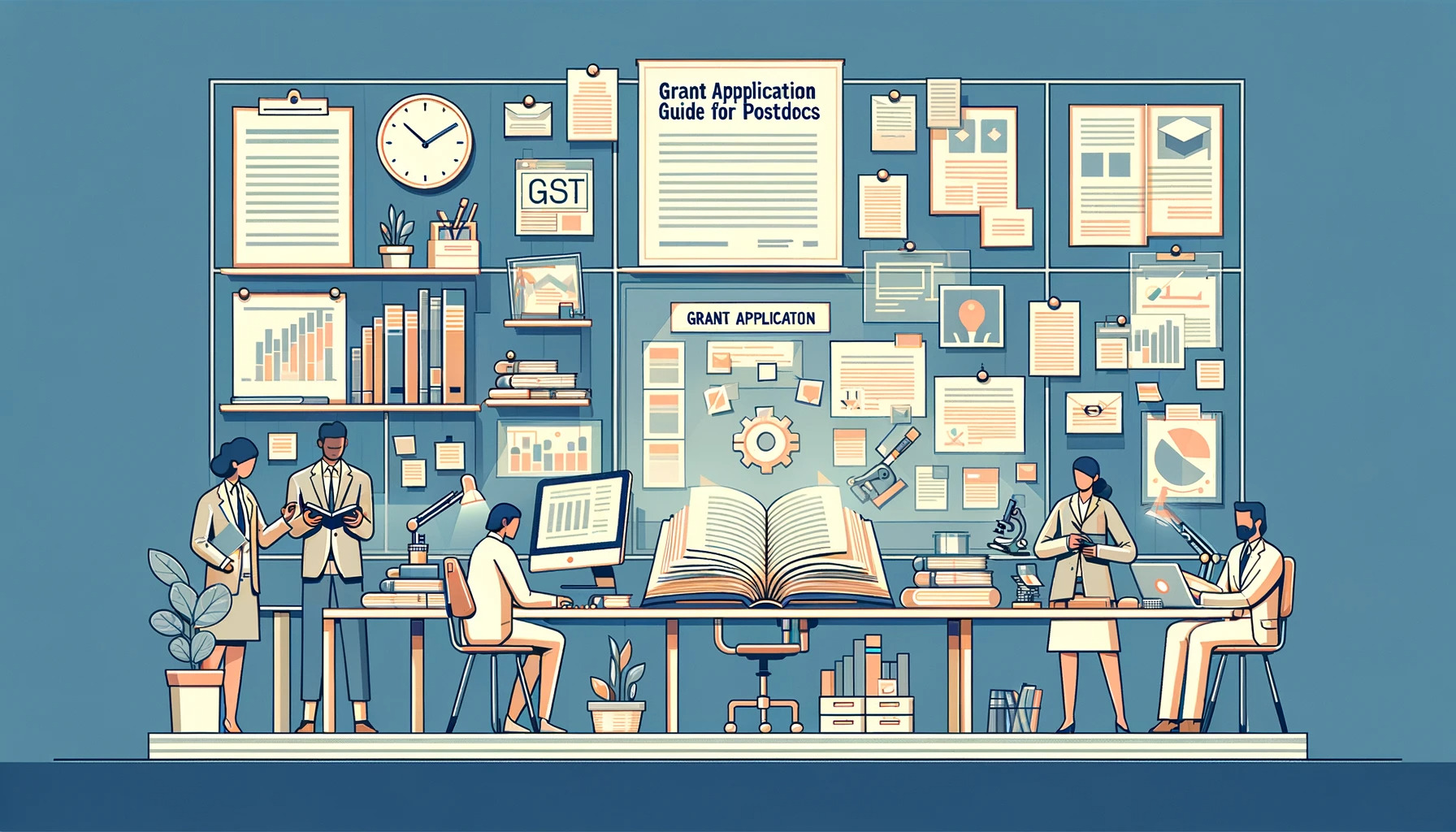
まず、助成金の探し方について。
これには、幾つかの方法があります。
1. 学内の公募情報
最初に、所属している研究機関の公募情報を確認するのが一番確実です。
恐らく、どの大学や研究機関にも助成金の公募情報をまとめたサイトがあると思います。
ここを確認することで「施設内の締め切り」や「施設内の人が必要な書類」などの情報が具体的に分かります。
しかし、デメリットとして、比較的よく知られた助成金しか掲載されないので、ねらい目の助成金が見つけにくいです。
ここで言う「ねらい目の助成金」とは、応募資格が厳しく、応募の母集団が少ない、だけど自分が運よく応募資格を満たしているものを指します。
2. 所属学会の公募
各学会でも研究留学向けの助成金を公募していることがあります。
その場合、大抵は学会員であることが条件だったりするので、割とねらい目です。
3. 助成金・奨学金のまとめサイト
地道な作業ですが、「まとめサイト」で自分が応募出来そうなものを探すのも一手です。
具体的には、私は以下のサイトで自分が応募できる助成金・奨学金を見つけてきました。
学内選考について
「科研費」や「学振」の時もそうでしたが、助成金の申請書を作る時は多くの場合で、推薦者を一人立てる必要があります。
そして、留学の助成金に関して言うと、推薦者の肩書があらかじめ一つに指定されており、さらには「一人の推薦者が推薦できるのは一人まで」というルールが設けられていることが多いです。
つまり、そのような場合では学内選考によって「推薦する応募者を一人」決める必要があり、学内推薦をもらってから初めて財団に応募することが出来ます。
大抵の場合、学部毎に1人応募できますが、指定された推薦者次第では、大学全体で応募できる候補者が1人だったりもします。
今回、「科研費」や「学振」の時にはなかった、この「採択までの2段階構造」に大いに悩まされました。
受入承諾書について

名称は違えど、どの財団も海外ラボの「受入を証明する書類(受入承諾書)」を求めてきます。
そのため、私は申請する助成金をリストアップし、それぞれの財団に向けた「受入承諾書」を一気に作成しておきました。そして、それらを留学先の多忙な PI に送付し、まとめて1回で署名をもらいました。
「受入承諾書」の作成については、上原記念生命科学財団が提供する「見本」がとても参考になります。
力の入れどころ(個人的な見解)
実は、研究者向けの留学助成金のうち、海外学振と上原記念の2つだけで大半の採用枠をカバーします。
なので、この2つの申請書は特に頑張りどこだと思います。
ただ、それぞれの注意点として、海外学振は締切が5月で早いのと、上原記念は学内選考が必要です。
実際、私はラボの内定を頂いたばかりだったので、海外学振の締切には間に合いませんでした。
また、上原記念も言うて締め切りが9月なので、大半の採用がその年度の前半6カ月で決まってしまうことを予め心得ておきましょう。
応募資格はその都度, 事務局に問い合わせるべし

応募資格は何回読んでも後ろから読んでも、自分が条件に見合うのか悩ましい時があります。
そういった場合は、財団ホームページの「Q&A」や「よくある質問」を熟読し、それでも解決しない時は躊躇せずに財団側に連絡してみましょう。
例えば、私自身の経験で言うと、助成金の応募資格には「留学経験がないこと」と明記されたものが幾つかありました。
私は幼少期に数年間アメリカに住んでいたので「応募は無理なのか・・・」と勝手に解釈していましたが、同じ事が書いてあった助成金があまりに多ったので「これはヤバい」と思って事務局に直接問い合わせてみました。
そうしたところ、多くの場合で「留学経験=研究留学の経験」と定義していることが判明し、問題なく応募出来ることが分かりました。
その他にも、色々と悩ましい応募資格があったので、その都度、事務局に問い合わせています。
個人的には「絶対無理でしょ」と思っていても、何だかんだ「とりあえず応募していいよ」という財団側のお返事を頂くことが多かったように思います。
申請者数について
コロナ禍の影響で「2020年は申請者数が減るだろう」と勝手に考えていましたが、公表された海外学振のデータでは、そんなこともなかったようです。
具体的には、令和3年度の申請者数の合計は例年と同じぐらいで759人でした。
ねらい目
繰り返しになりますが、応募資格が厳しい(=門戸が狭い)けど、自分が条件を満たしている助成金が最もねらい目です。
それらに該当するのは主に「研究テーマが指定」されていたり、「学会員限定」の助成金だと思います。
例えば、「リリー・オンコロジー・フェローシップ・プログラム*」という助成金は日本呼吸器学会 腫瘍学術部会会員限定で、さらに研究分野が「呼吸器病 腫瘍関連分野」と指定されており、私にとっては大変ありがたい「ねらい目」の助成金でした。
*残念ながら、現在は応募を終了されているようです。
重複受給について
歴戦の猛者は、少しでも多くの助成金を確保したいと考えると思います。
複数の財団から採択された場合、重複受給できるかどうかはそれぞれの募集要項に大抵載っています。
そして、ほとんどの財団では「1人でも多くの個人」に助成金が行き渡るように配慮し、何かしらの制限を設けています。
その他
助成金をたくさん応募した感想として、やはり採用枠が一桁のものはかなり厳しい戦いでした。
ただ、数を稼ぐことはもちろん大切なので、「海外学振」や「上原記念」以外の助成金を目指す場合は、たくさん申請書を作っておくことをオススメします。
もしくは、前述した「ねらい目」の助成金があるか必死に探しましょう。
あくまで参考値ですが、メジャーな助成金の採択率は海外学振が20%、上原記念が30-40%ぐらいだと言われています。
ただ、上原記念に関しては学内選考が必要なので厳密にはもっと低いかもしれません。
最後に

今回のように、年間を通して何かしらの申請書を書き続けたのは初めての経験でした。
また、そこに肺がん診療に加えて、新型コロナの診療などもあったため、体力的にもメンタル的にも、まあまあ鬼畜でした。
そんな中でも、1件のみとはいえ、大型の助成金を獲得できたのは本当に嬉しかったですし、採択のメールを頂いた時は嬉しくて絶叫しました。
今回の記事では、私が「経験したこと」や「振り返ってみて考えたこと」などを余すところなく書きました。
これから研究留学を目指している方々の力に、少しでもなれたら幸いです。
冒頭で述べた通り、次の記事では私が見つけた助成金・奨学金をリストアップしたので、自分に合ったものがないかチェックしてみて下さい。

以上、最後まで読んで頂きありがとうございました!