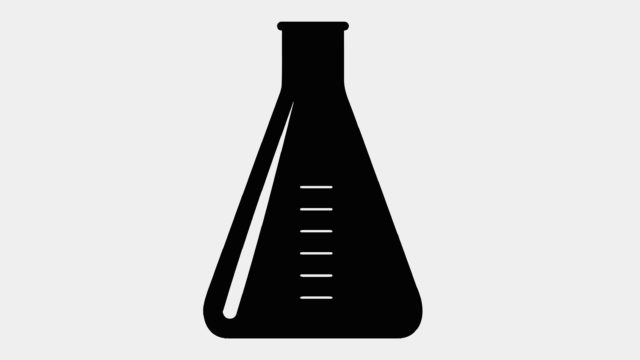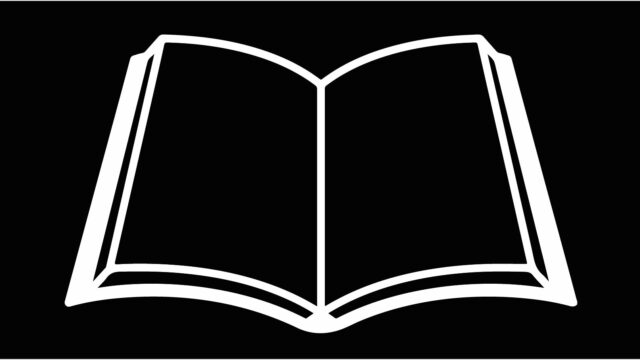大晦日・元旦にもラボで実験を行い、幸いにも大学院2年目の年始明けに基礎実験がひと段落つきました。
そこからさらに、約2か月間かけて初めての基礎論文を書き上げ、2月末に恐れ多くも Cancer Cell に論文を投稿しました。
ここまでは、よくあるサクセスストーリーのようですが、ここからが長い戦いの始まりでした・・・
そして、未だに先が見えない状況であり、今回はあくまで実体験を記録に残すことが目的です。はあ。
連続リジェクト
Cancer Cell は約1週間で editorial-kick でした。
これは予想通りだったので、特にダメージもなく、そのまま形式だけ整えて次のジャーナルに投稿しました。
しかし、ここでも1週間で editorial-kickとなり、ラボのボス、コラボレーター(共同研究機関)とも相談し、急ぎたい気持ちを抑えつつ、追加実験を2カ月間かけて行いました。
追加実験のおかげで、話の流れが以前よりスムーズになったと確かな手応えを感じつつ、某有名ジャーナルに投稿、さらには来日していた編集長にも直接アピールしましたが、あえなく1週間でリジェクト。

その後、マイナーな修正を加えつつジャーナルを変えたり、transfer を行ったりしたところ、計6連続で editorial-kick となりました。
心の葛藤

負け戦がこうも続くと、否が応でも自分の研究そのものを否定された気持ちになります。
- 自分の今までの努力は一体何だったのか。
- 研究への膨大な時間をもっと臨床に向けていれば、患者さんのためになったのではないか。
- 臨床と研究の両立は流石に・・・。
- データの半分以上をそぎ落として、早くこの状況が終わるところに・・・。
- こんなに辛いなら、やっぱり研究留学は・・・。
などと頭をよぎります。
そんな時に、自分の頭の中で絶えずひしめいていた2つの単語「論文 リジェクト」をふとネットで検索したところ(少し病んでますね)、諸先輩方の様々な実体験を読むことが出来ました。
どうやら、諦めるにはまだまだ早かったようです。
冷静になり少し落ち着いて考えると、「まだ出来ること」がたくさんあることに気が付きました。
まだ、先が見えない暗いトンネルですが、決意あらたに、今後も編集者に蹴られ続けていきたいと思います。
ちなみに、当時私が閲覧したのは以下のサイトです。
ただし、念のためお伝えしておきますと、このサイトは暗号化(SSL; Secure Sockets Layer)されていないため、閲覧は自己責任でお願いします。
日本の科学と技術. リジェクトへの怒り・落胆【論文を出す力】
(http://scienceandtechnology.jp/archives/12354)